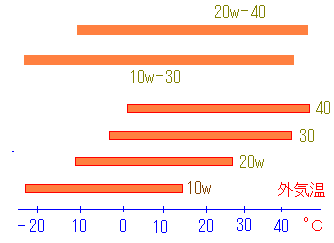
つまり、外気温で冷却するということですから、外気温が極端に高かったり低かったりしますと
(油温をある程度エンジンの潤滑経路の構造から制御※しているにもかかわらず、)
そのオイルの粘度によって十分に潤滑を行える範囲外になってしまう事が起こります。
※温度の調節に関しては「温度センサー」「サーモスタット」などが使用されており昔は、季節の気温差によって夏用のオイル、冬用のオイルがあり、
冷却ファンのON−OFFの作動や水流の制御をしています。ただし、制御できる範囲は
外気温の状態に左右されます。
それぞれの詳細はそのページでみてください。
エンジンの設計では
基本的には外気温度20度Cから25度Cでエンジンを動かし
エンジンオイルの温度が80度Cから100度Cになるあたりに
一番効率の良い燃焼状態になるようにしています。
油温や水温の制御も燃焼効率から設定されます。
ですから、
真冬にオイルがあまり低温になりすぎますとグリース状になったり固まって
吸い上げられず、しばらくオイルがないような状態で潤滑出来ないのでは困りますし、
反対に真夏の巡航(渋滞)状態でオイルが高温になって各部へのオイル油膜が薄くなり過ぎ
油膜保持が出来ないようでも困るわけです。
使用可能温度表はある教育関係の教科書に下記のように記載されていましたが、
理想的な使用状況で運転されることはごく短期間ですし、
どうも、根拠というか、何に基づいてこの表を記載しているのか判らないと残念ながら思いました。
理由の一つとして考えられますのはなお、オイル側での技術的な進歩は、精製の問題と添加剤開発などによってきているようです。
設定当時のエンジンに空冷エンジンも入れられていたからと考えられます。
水冷ならば水温はラジエターキャップで圧力をかけられていても
100度を大幅に超える事はありませんが、
空冷ですとオイルは100度など簡単に超えるからです。この表は10年以上も昔から使用されているそうで、
そのころのSAEグレードはSGかSFが最高のグレードですし、
オイル自体が鉱物油基準で作られていますので、主に鉱物油の基準表とも言えそうです。
オイルによる使用温度帯はこちらの下段にあります。
オイルの粘度が温度で変わると言うことは、
特に摩耗(=油膜保持)とポンピング(=低温での流動性)という側面から
鉱物油では粘度が大きなウエイトを占めておりますので
機器の保持という観点から守られないといけない事柄になってしまいました。ポンピング速度も重要でして、確かに当時のオイルやエンジンの構造から考えますとこういった表が出来たいきさつも判る気がします。
ドライスタートは通常の運転中の摩耗の300km分とも1500km分とも言われています。
低温の際に低粘度油の方が当然ポンピングが容易で
素早く各パーツへオイルが運ばれますから
通常使用であまりにも硬いオイルを使うというのも考え物かもしれません。
なお、ドライスタート防止用に効果のある添加剤を利用するのも一つの方法です。
工業製品が時代背景を反映している事がよくわかります。
基準が現在と比較しますと相当低いレベルでオイルが作られていましたので
外気温の変化が直接オイルに影響するような状況だった事がわかります。
それが現在も技術的な進歩があっても
見直されず、そのまま記載されているようです。
PC関係でも次から次と新しい規格が出てきて、同じようにめまぐるしいまでの技術的進歩がありますが、
こちらはすんなりと理解されていますので、多少違うとらえ方になってしまうのかもしれません。
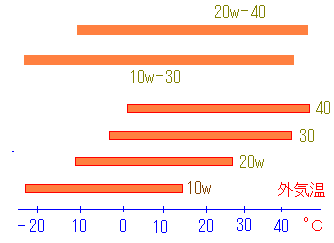
また、表以外に具体的にオイル粘度を指定して記載していることもあります。
現在でも例えば「10w−30」「5w−30」などというようにそれを使用するように指定する場合も多く見られるようです。
一般的には「マルチグレードオイル」という幅広い温度帯に対応したオイルが出来ていますし、
(シングルグレードオイル自体がほとんど見うけられなくなっています)
オイルの性能も向上しましたので外気温の変化幅にはあまりとらわれなくてもいい状況になってきています。
ただし、オイルの性能向上は、裏を返せば、オイルの性能がエンジンの要求に応えられなくなったからとも言えますので
リスクマージンは十分取る必要はありそうです。
と言うのも、短期間ではオイルの劣化も粘度変化も少なく、油膜の形成に影響が少ないのですが
表が作られた当時の規格には現在のSL規格以上と異なり長期耐久性の規定がなかったわけですから、
使用初期に優秀な性能があっても、その場限りという商品もあり、商品自体の格差が相当あったと思われるからです。
今は、普通の巡航型使用中心の条件と「シビアーコンデション」と言われる走行とを分けて記載されております。
まあ、通常は一般的使用とはいえ、シビアーに近い使い方をされているユーザーが多いので、
シビアー条件の1.5倍程度で交換時期を見れば良いでしょう。
ただし殆どのメーカーは最長使用期間を1年間としているので
1年に1回は交換されるに超したことはありません。
(私はデーター取りテスト車ですから2年ぐらい走りますが・・・)
オイルの冷却としてはターボ車のように、はっきりと判るような大型のオイルクーラーではなくても、
オイルフィルターの取り付け台座部分に小型のオイルクーラーを取り付けているエンジンも多く、
そういった機構からも低粘度オイルを使用し、省燃費に貢献するように考えられるようになってきました。
ただし、外気温(と水冷などのクーリングシステム)に影響を受けることは依然としてあり、仕方ありません。
外気温によるSAE粘度番号により
オイルパンの油温は大体冷却水の最高温度ということもあり100度Cの時を想定しており、
HTHSの基準となるカムなどの油温は150度Cと想定してこの時の油膜が2.6以上必要と言われています。
シリンダー内部では240度前後まで金属部の温度が上がる箇所もあり低粘度油にすることの理由として重要なのは省燃費性という事になり
(燃焼ガス温度は800度C以下と考えられています。)
通常の鉱物油ではこの部分では燃えてしまう事になります。
このあたりの温度は合成油での引火点とも重なってきます。
例えば某メーカーの10wのシングルグレード鉱物油で150度のHTHS粘度を見てみますと、
約2.9ほどありますので、これならば外気温40度Cまでなら使用可能となってしまいます。
つまりこのオイルは10w−20or30の粘度グレード帯にあるわけです。
オイルの使用可能外気温としてはOKと言うことです。ところが、上記の表では「使用不可」で、外気温15度Cまでしか認めていません。
ただ耐久性評価としては
使用して行く内に起きる劣化を考える必要があり
まだまだ通常用には使えないと言えます。
省燃費性から0w−20など、当時は考えられない程の低粘度油が使用されていますが、もちろん、2001年の夏のような暑さですと、日中は舗装道路上の外気温は40度Cを超える日が多かったようでしたから、
エンジン自体の油圧の低下が起こりやすくなっていますので、長寿命化に対しては一抹の不安を拭いきれず、
省資源という観点からはオイルの早期交換をしてしまうことで、帳消しになってしまうようにも思えてしまいます。
またオイル自体の減りから考えますと
蒸発量もどちらかといいますと低粘度油が高粘度油より多く消費します。
(ただし、油圧機構を伴う場合は、指定粘度を使用しないと逆に故障します。)日本の場合はエンジンなどを末永く大切に使用する方が、
よっぽど新車に乗り換えるより環境に優しいはずなのですが
それでは経済活動に悪い影響が出てしまうのでしょう。5w−20の低粘度オイルを標準で使用しているエンジンは大体平成10年頃から出てきていますし、
0w−20指定のエンジンもこれからも増えてゆくことと思います。で、0w−20を純正で粘度指定しているエンジンに2001年度時点での低粘度オイル使用例です。(資料:カストロール)
別のメーカーの0w−20の粘度のオイルを使用しますとメーカー保証は付かなくなります。
(ただし保証期間や保証距離を過ぎていますと純正でも保証は付きません)
これは
「それ以外のオイルでは試験していないので保証できません」という断り文句でして
まあ余程ひどいオイルでなければ
0w−20でも5w−20でも5w−30でさえも許容範囲として
使用することは問題ないと考えられています。
ただしオイルの品質は重要ですから
「ILSAC GF−4以上の規格」がある、あるいは同等のオイルを使用してください。粘度を0w−20から5w−20や5w−30に変えますと
外気温がマイナス以下になる低い場合などでは
始動時の粘度が多少変わりますので
暖気出来るまではエンジンの回りが多少重く感じる事があり
省燃費性としても悪くなる事がありますが
フィール的な要素ともなりますので実際に使用されて比較されると良いでしょう。なお0Wと5Wの違いを簡単に表現しますと
−35度Cで測定されるオイル粘度で固いか柔らかいかで、
その基準値に合格すれば0Wで、
その基準値より固いともう少し暖かい(といっても−30度Cですが)温度で
基準値にあれば5Wとなるだけです。
同じように調べて
−30度Cでも固いと10W(−25度Cの合格ライン)、15W(−20度Cの合格ライン)、
20W(−15度C)、25W(−10度C)と最低温度での粘度が高くなり
つまり、冬が寒くない地域ではそれぞれが選べると言うことになります。
(反対に○W−XXの「XX」は熱い気候の地域では重要になります)
SAEのページにも下記の表は記載していますが、この表も粘度の基準をあらわしているだけで
それ以外の評価を含んでいるわけではありません。
2001/06までのCCS粘度分類(併記の場合は括弧内が新しい基準を記載しています)
| エンジンオイル | ||||
| ASTM試験法 | D5293 | D4684 | D445 | D483 |
| SAE粘度
グレード |
低温側
2001/06まで (2001/07より) |
ポンピング粘度 | 高温側 | 150°C |
| 規定温度での最大粘度
SAE J300 |
J-300規格=60000mPa・s | 動粘度cSt(100°C)
以上mm2/s<未満 |
HTHS粘度cP | |
| 0W | 3250mPa・s−30°C
(6200mPa・s -35°C) |
60000mPa・s(−40℃) | 3.8 ー | ー |
| 5W | 3500mPa・s−25°C
(6600mPa・s -30°C) |
60000mPa・s(−35℃) |
3.8 ー | ー |
| 10W | 3500mPa・s−20°C
(7000mPa・s -25°C) |
60000mPa・s(−30℃) |
4.1 ー | ー |
| 15W | 3500mPa・s−15°C
(7000mPa・s -20°C) |
60000mPa・s(−25℃) |
5.6 ー | ー |
| 20W | 4500mPa・s−10°C
(9500mPa・s -15°C) |
60000mPa・s(−20℃) |
5.6 ー | ー |
| 25W | 6000mPa・s −5°C
(13000mPa・s -10°C) |
60000mPa・s(−15℃) |
9.3 ー | ー |
| 20 | ー | ー | 5.6< 9.3 | 2.6 |
| 30 | ー | ー | 9.3<12.5 | 2.9 |
| 40 | ー | ー | 12.5<16.3 | 2.9(A)※ |
| 40 | ー | ー | 12.5<16.3 | 3.7(B)※ |
| 50 | ー | ー | 16.3<21.9 | 3.7 |
| 60 | ー | ー | 21.9<26.1 | 3.7 |
※(A)= 0w、5w、10w-40 (B)=15w、20w、25w-40、40
センチポアーズ(cP):cStを密度で割った粘度の単位
cP=mPa・s
cSt=mm2/s
オイルの固さと外気温
鉱物油と合成油が同じ粘度グレードなのに、どうも合成油の方が柔らかく感じてしまうといった事が起こります。
鉱物油と鉱物油としての超精製油と比較しますと、超精製油の方が堅いような感覚を受けますし、
合成油同士でも、PAO(ポリアルファオレフィン)系とエステル系の含有量の差によって粘度が違うように感じることがあります。
超精製油で10w−40の粘度のオイルを例えば軽自動車で使用しますと、夏ならばさほど問題なく、多少重いフィーリングを
受けるだけなのですが、冬はかなり固く感じ、暖まるまで別のエンジンかと思えるほど
粘性抵抗を強く感じます。
どちらかと言いますと、超精製油は粘度的には夏向きと思われます。
ですから、軽自動車では夏に5w−30で十分なのです。
(5w−30は冬では重く感じます。)
一方、エステル、PAO系は元々0wか5wとして低温時の流動性が良好なオイルとして宣伝されていたように、
外気温による低温時に特に柔らかさを感じるオイルと思われます。
かといって、高温時の油膜保持能力にも優れていますので、安心して使用出来る商品が増えてきております。
ですが、それでも粘度指数向上剤などポリマー成分が剪断されますし、水分や未燃燃料などの混入で
粘度低下を起こしますから、長期使用の限界はあります。
(不要・使用済み成分を濾過し、新たに添加剤を入れることで再利用は十分可能です。)
ですから、この「粘度」という数値がどのようにして決められているのか、実際に装置などを通して
みてみたほうが、わかりやすく思えます。
本当に外気温が下がって、オイルの粘度が上昇し、水飴状になってしまい固く感じる事は
新油では滅多になく、こういった現象が起こるとすれば、
保管時の外的環境によって添加剤成分がゲル化したと言う場合だけと思われます。
(部分的に起こることはあっても全体がゲル化することは無いでしょう。)
工事中